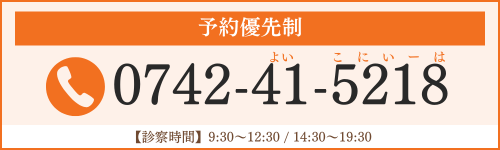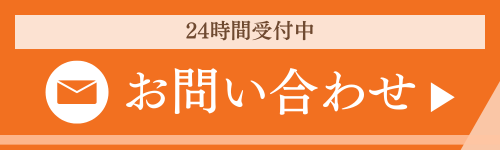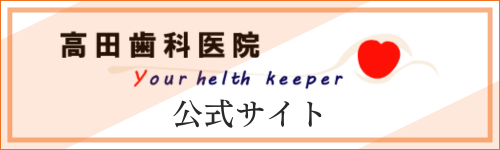叢生|奈良市の矯正歯科なら【高田歯科医院】

叢生とは何か
叢生(そうせい)とは、歯が正常な位置に並びきらず、重なり合ったり不規則に並んだりしている状態を指します。いわゆる「乱ぐい歯」や「八重歯」なども叢生の一種です。歯がでこぼこしていることで、見た目に影響するだけでなく、歯磨きがしにくくなるため、虫歯や歯周病のリスクも高まります。
また、噛み合わせのバランスが崩れることにより、あごの関節に負担がかかる場合もあります。叢生は比較的多く見られる不正咬合のひとつで、子どもから大人まで幅広く矯正治療の対象となる症状です。

叢生になる原因
先天的な原因について
叢生の発症には、もともとの顎の大きさや歯のサイズなど、遺伝的な要因が関係しています。たとえば、顎が小さいにもかかわらず歯が大きい場合、歯が生えるスペースが足りずに、重なり合いねじれて生えてしまいます。
また、歯の本数が多い「過剰歯」や、歯の位置がずれて生える「異所萌出(いしょほうしゅつ)」なども先天的な原因として挙げられます。こうした骨格的・形態的な問題は、早期の診断で把握できる場合もあります。

後天的な原因について
後天的な要因としては、指しゃぶりや爪噛みなどの癖、口呼吸、頬杖といった習慣があげられます。これらは歯列や顎の発育に偏りを生じさせ、叢生の引き金となることがあります。
また、乳歯が早く抜けてしまった場合や、虫歯によって咬み合わせが乱れたまま成長すると、永久歯の生える位置が確保できず、結果的に叢生を引き起こすこともあります。予防のためには、子どもの頃から口腔習慣に注意を払うことが大切です。

上顎前突を治せる矯正方法
叢生は、比較的多くの症例で矯正治療が可能な不正咬合です。当院では、症状の程度や歯の状態に応じて、ワイヤー矯正とマウスピース矯正(アソアライナー)のいずれかをご提案しております。
ワイヤー矯正
叢生は、比較的多くの症例で矯正治療が可能な不正咬合です。当院では、症状の程度や歯の状態に応じて、ワイヤー矯正とマウスピース矯正(アソアライナー)のいずれかをご提案しております。

マウスピース矯正(アソアライナー)
透明なマウスピースを用いて、計画的に歯を動かしていく矯正法です。1日20時間以上の装着が推奨されており、2週間〜1か月ごとに新しいマウスピースに交換していきます。治療の途中では、歯の動きに合わせて「リファインメント(再評価とマウスピースの再作製)」を行うことで、より精密な仕上がりを目指します。軽度〜中度の叢生に適応されることが多く、審美性や取り外しの利便性を重視される方におすすめです。

どちらの方法でも、事前の精密検査とシミュレーションを通じて、最適な治療計画を立案します。治療方法の選択に迷われる場合も、まずはお気軽にご相談ください。
当院の叢生の治療例
39歳女性
before

after

備考
上下顎とも歯列弓が狭いので、小臼歯抜歯の矯正をすると舌房(舌の置き場)が狭くなり、息苦しくなってしまう。
そのため小臼歯抜歯はせず、上下顎とも前方、側方拡大し歯列を整えていった。
具体的な治療方法
1,014形状記憶合金ワイヤーでレベリング
2、2.上顎左右MOGW、下顎左側MOGWで大臼歯を奥に送り歯列を前後的に拡大していく
3、3.上顎はマリガンを併用し側方にも拡大し、歯列弓にずれている歯を入れていく
4、4.上下顎MEAWに交換しアーチフォームを整え仕上げていく










© 2025 高田歯科医院 矯正専門サイト All rights reserved.